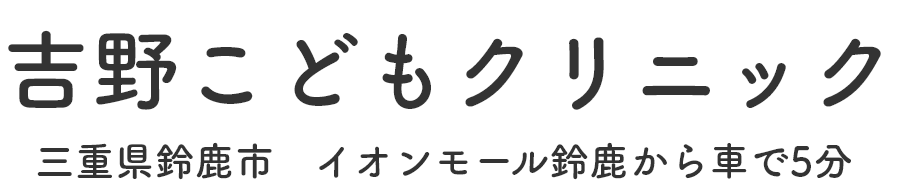アレルギー科
アレルギー科について
-

当クリニックは、お子さまのアレルギー症状を鎮めながら、それぞれの体質や生活環境を踏まえて、対処方法を見つけるサポートをしています。アレルギーとは、アレルゲン(アレルギーの原因物質)に免疫が過剰反応して身体に弊害が起きることを指しています。発症には様々な要因が絡み合っていることが多いので、個々に対応していくことが重要なのです。
-
アレルギー反応の原因
アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)が身体に入りこみ、アレルゲンとIgE抗体が多く結びつくほど症状が出やすくなります。しかしながら、抗体が免疫として有効に作用することもあります。そのため、IgE抗体が多いからアレルギー反応が出ると確定できるわけではありません。あくまでもアレルゲンへの過剰反応だけが問題です。また、アレルギー反応は遺伝的要素や環境的要素にも左右されることが知られています。
よくある疾患と治療法
-
食物アレルギーについて

乳幼児にとってアレルギーの要因となる代表的な物質には、卵、牛乳、小麦があります。また、大豆やソバなどもアレルゲンとなりますし、年齢が少し上がると、木の実などのナッツ類やピーナッツ、カニやエビ、イクラなども対象となります。学童以降はニンジンやキュウリ、スイカやメロン、セロリやパセリ、モモやリンゴなどで喉に痛みやかゆみなどが現れる口腔アレルギーが増える傾向が見られます。口腔アレルギーは花粉症との関係が指摘されており、食物依存性運動誘発アナフィラキシーも学童期以降に増えます。
お子さまにアレルギー症状が出たことで、疑いがある食べ物を徹底的に口にしないと考える親御さまもいらっしゃるようですが、極端な対処はお子さまにとって良いとは言えません。そのため当クリニックでは、問題がない範囲で食べられるものは食べる、という考え方をおすすめします。 -
治療法
アレルギーの原因となる食べ物への対処には、アレルギー症状が出ない量を考えながら摂る「部分除去」と、アレルゲンを全く食べなくする「完全除去」があります。幼少期には症状が出ていても、年齢が上がると解消することも多いので、何がアレルゲンであるか、アレルギー症状の重さを踏まえながら一緒に考えましょう。また、昨今は意識的にアレルゲンを少量ずつ取る経口免疫法も用いられています。
-
アトピー

アトピー性皮膚炎では、皮膚表面がカサカサになってむける「落せつ」や、皮膚の赤みである「紅斑」、ぶつぶつが現れる「丘疹」などの症状が見られます。また、かゆみや発疹が出る状態を、良くなったり悪くなったりしながら慢性的に繰り返す点も大きな特徴です。乳幼児期に発症することが多く、小児の1割程度で見られます。成長の過程で改善する例が多いですが、成人になってからも継続するケースもあります。
乳児湿疹は一過性のものですが、しっかり治療に繋がらないと、症状が長引いて皮膚を掻き破り悪化する例が増えます。乳幼児の場合、乳児湿疹とアトピー性皮膚炎の識別は困難ですが、治療で症状が治まっても再度症状が出て繰り返すようならアトピー性皮膚炎を疑います。
アトピー性皮膚炎と乳児湿疹はかゆみの制御や皮膚の状態維持は可能ですから、ぜひ適切な治療を受けてください。 -
治療法
アトピー性皮膚炎の治療は、薬物療法で炎症を抑え、アレルギーの要因を発見して取り除き、お肌の清潔さや潤いを保つ、という3点で成り立ちます。これらをバランスよく継続することが治療の基本とお考え下さい。また、ステロイド外用薬で炎症を抑える治療はするものの、ステロイドに頼らない日を増やすよう意識すること、医師との相談なく治療をやめないこと、状態を良くして維持するモチベーションを保つことなどの意識面も欠かせません。
症状が激しければ、内服する抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬なども処方しますが、日々のスキンケアをおこたらないよう注意しましょう。 -
アレルギー性鼻炎

お子さまは大人に比べるとウイルス感染のリスクが高く、繰り返す傾向も見られます。学校や幼稚園、保育園など集団の中にいる時間が多いこともあって、風邪による鼻水やくしゃみなどが長く続くことも多い実情もあります。このような理由から、お子さまご本人や親御さまにとって、鼻水や鼻づまりが、風邪などのウイルス由来なのか、アレルギー性鼻炎なのかを見分けるのは非常に困難です。また、お子さまや親御さまだけでなく、医療機関でも風邪の症状とアレルギー性鼻炎によるものが十分に区別されていないケースも見られます。そのため、当クリニックのようにアレルギー科を有する医療機関で専門性を持って診ることが重要です。お子さまに鼻水や鼻づまりなどが継続して見られる場合、ぜひ当クリニックを受診してください。
-
治療法
アレルギー性鼻炎に対しては、ロイコトリエン受容体拮抗薬や抗ヒスタミン薬の内服と、ステロイド系の点鼻薬による治療が中心です。どちらも根本治療にはなりませんが、わずらわしい症状を抑えることができます。
-
気管支喘息

気管支喘息は、深夜や明け方に発作を起こすことや、「ゼーゼー」、「ヒューヒュー」と表現される「喘鳴」などの症状が起きることで知られています。そもそも「気管支」とは、気管の先で左右の肺につながる部位です。その気管支が物理的に狭まって空気が通りにくくなることで、発作や喘鳴などの症状が現れます。
とはいえ、お子さま本人や親御さまにとって、風邪による咳なのか気管支喘息による喘鳴なのかを見分けることはできません。また風邪以外の要因でも喘鳴は起こります。さらに、小さいお子さまは、横にしようとしたときにぐずったり、咳込んだことから嘔吐したりすることもあり、親御さまからするとそのようなときのしぐさから「気管支喘息では?」と思うこともあるようです。そのため診断にあたっては、風邪の症状がない場合にも喘鳴があるか、身体を動かしたときや興奮したときに症状が出るか、何らかのアレルギー症状があるか、などを考慮に加えます。 -
治療法
気管支喘息の治療は、発作への対処と、日常の中で発作を置きにくくするものとに大別されます。
発作への対処としては、気管支拡張薬を使用することが多く、種類としては吸入薬や内服薬のほか張り薬があります。日常で発作を抑えるために行う治療では、ステロイド薬やロイコトリエン受容体拮抗薬で炎症を抑えることが中心です。
「ステロイド」という名称の薬剤に抵抗感を持つ方も少なくありませんが、医師の指導に沿って使用していれば、恐れるような副作用はありません。また、ロイコトリエン受容体拮抗薬は軽症のうちに使用することで効果を得やすいことがわかっていますし、安全性の面でも評価が高いので、処方回数が多い薬剤です。
小児喘息について

お子さまは風邪の症状として「ゼーゼー」することがあり、気管支喘息でなければ成長とともに見られなくなります。しかし、気管支喘息であれば、気道の炎症が慢性的に続きますし、気道が徐々に変化して呼吸機能が低下していくことがあります。このような状態を避けるためにも、軽症のうちに適切な治療を受け、継続していくことが非常に重要です。
小児喘息